ゾロアスター教(拝火教)
ゾロアスター教は前7世紀頃にメディア生まれの宗教改革者ゾロアスターがおこしたイラン発祥の宗教である。ユダヤ教やキリスト教に影響を与えた。なお、ゾロアスタ-の活動時期については、前1200年頃など異説は多い。アケメネス朝ペルシアで保護され、ササン朝では国教とされた。中国には北魏の頃に伝わり祆教(けんきょう)と呼ばれた。火や光の崇拝を重視したので、拝火教とも呼ばれる。
ゾロアスター
ゾロアスター教のは、メディア出身の宗教改革者ゾロアスター(前7世紀後半~前6世紀前半)が、古代イランの二元論的な民族宗教を救済宗教へと高めた。
善悪二元論
ゾロアスター教は、善悪二元論に基づき、世界を善の神アフラ=マズダと悪の神アーリマンとの対立からとらえる。アフラ=マズダは最高神で、光明・善の神のに対し、アーリマンは暗黒・悪の神である。数千年の期間でこの二つの神が戦い争っている状態にあるとした。
最後の審判
善の神アフラ=マズダと悪の神アーリマンが絶えまなく戦っている状態であるが、両者の優越は3000年ごとに交替し、9000年または1万2000年目の戦闘に善の神アフラ=マズダは、悪の神アーリマンに勝利した。世界は大火災による終末を迎えるが、しかし善き人々の霊魂は最後の審判をへて救済されるとした。
歴史の4期間
- 第一期:善の神アフラ=マズダの精神的創造期
- 第二期:物質的創造期
- 第三期:悪の神アーリマン
- 第四期:ゾロアスターによる支配
ミトラ、アナーヒター
光明神のミトラや水神で大地母神のアナーヒターの信仰もおこなわれた。
ユダヤ教やキリスト教への影響
ゾロアスター教の救済はユダヤ教の二元論的終末論につながり、キリスト教にも受け継がれた。また、マニ教にも影響を与えた。
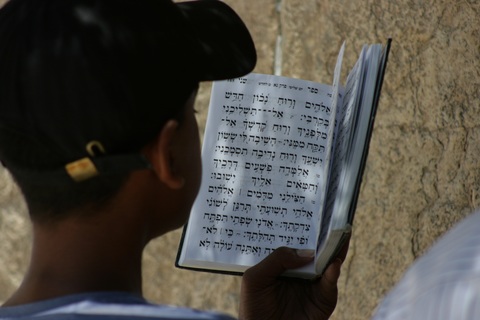
ユダヤ教
ニーチェ
ドイツの哲学者ニーチェにも多大なる影響を与え、『ツァラトゥストラかく語りき』の主人公ツァラトゥストラはゾロアスターからとった名前である。
HitopediaShop
現在の信徒
現在でもゾロアスター教はインドのムンバイやイランの中部で信仰されている。総勢は10万人から15万人と言われている。
